|
| �@�E�T�o |
|
Scomber japonicus
�X�Y�L�ڃT�o�ȁ@�}�T�o�A�S�}�T�o�E�E�E
�@
���{�S��ɍL�����z���A�t����Ăɂ����Ėk��A�H����~�͓쉺����B�C�ʂ̕\�w�߂����Q�ƂȂ��ĉ�V���Y�����͂R������W���ōő�50�p���A���̏��̗ǂ��H���{�ł��B
�A�W�E�T�o�E�C���V�ƂƂ��ɂ����Ƃ��|�s�����[�ȋ��ł��B
�V���T�o�A���Ă��A���X�ςȂǐH�ו������낢�날��A��Ɏh�g�ŐH�ׂ��邪�A�I�̐�������ƌ�����悤�ɁA�N�x��������̂������B |
 |
| �@�E�T���} |
|
Cololabis�@saira
�T���}��
�O�m���̕\�w���ŁA��Q�𒅂����ċG�ߓI�ȉ�V���s���܂��B�Ă͖k�C���Ȗk�֓~�͐����{�ֈړ����܂��B
�~��a�̎R�ߊC�Ŋl���T���}�͎�������Ă��Ȃ��̂ŁA�|�Œ��߂ăT���}�����ɂ��鎖���ł��܂��B
�H�̃T���}�͎�������ĉ��Ă��A�ϕt���ɂ���Ɛ�i
�n���ł́u������v�Ƃ��Ăт܂��B |
 |
| �@�E�T���� |
|
Scomberomorus niphonius
�X�Y�L�ڃT�o���ڃT�o�ȃT������
�̂͑��G���A�������ÐF���_���̑���ʂɂV�`�W����ԁB���݂̕\�w�ɂ��݁A�~�G�͉��w�Ɉړ�����B���˓��C�ɑ����B�Y�����͂S�`�T���ŁA���p�ɓ����Ă���B�J�^�N�`�C���V���C���V�ށA�C�J�i�S�A�T�o�A�T���}����ߐH���鋛�H���B
�傫�Ȃ��̂ł͂P��������̂�����܂��B
�u�����v�Ƃ����̂́u�����v���Ȃ��ג����̌`��\���Ă���A�c���̎����́u�������v�́u�����v�������Ӗ������B
��ʂɃT�����͐����{�Ől�C�������A���ŒႢ�B
�T�����͎h�g�A�݂��Ђ��A���Ă����ɂ��ĐH����A��i�Ȗ��̋��ł��B�@
|
 |
| �@�E�V�C�� |
|
Coryphaena hippurus
�X�Y�L�� �V�C����
�����{�����B�A����ɂ����ĕ��z���A�����̕\�w����V���āA�C���V��g�r�E�I�Ȃǂ��a�ɂ��Ă��܂��B�g���[�����O��A�[�ȂǂŒނ�邱�Ƃ������A�̂͌��݂��Ȃ��G���ŁA���������I�X�́A�Ђ���������o���Ċp���邪�A���X�͊ۂ��̂������ł��B
���{���ʂł́A�g�E���N�Ƃ��Ă�A���h�g�≖�Ă��ŐH�ׂ��܂��B |
 |
| �@�E�V�^�q���� |
|
�J���C�ڃE�V�m�V�^�ȃC�k�m�V�^���A�J�V�^�r����
�֓��A�V���ȓ삩�瓌�V�i�C�ɕ��z���A���[�P�O�Om�Ȑ�̍��D��A���ɓ��p�̐��[�Q�O�`�T�Om�ɑ�����������B
�N���V�^�r�����͂��k�̖k�C���ȓ삩�琶�����Ă���B
�̂͑ȉ~�`�ŁA�w�r���ƐK�r�����q�������`�ɂȂ��Ă���B�L�ᑤ�̍��̑��͐Ԋ��F�ŁA���ᑤ�͔��F�ł���B
���ʂ̋��͌����擪�ɂȂ��Ă���̂ɑ��A��r�����̊�ł͏����ȗ��ڂ̂������Ɍ������ԂƂ������j�[�N��������B
����P�N�ő̒��P�Ocm�A�Q�N�łP�Scm�A�R�N�łP�Vcm�A�S�N�łQ�Pcm�ɐ������A�P�Tcm�O�ォ�琬�n���n�߂�B��ԂɁA�s���L�o�ŃS�J�C�Ȃǂ̑��їނ�A���^�̃G�r�E�J�j�ށA�L�Ȃǂ�H�ׂĐ�������B
|
 |
| �@�E�X�����C�J |
|
Todarodes pacificus
�c�c�C�J�ڃA�J�C�J��
�قړ��{�e�n�Ŋl��邪�A�O����k�C���͔ӏH����~�ɂ����ċ��l�ʂ������B
���̒����͖�30�����A�̂͊��F�Ŕw���ɍ��т�����܂��B���{���݂̊C���ɂ̂��Ėk��A�쉺����̂ŁA�G�߂ɂ���ċ���͈ړ�����ꏊ�ɂ���Đ����x���Ⴂ�܂��B��B�ߊC�̉��g�ȊC���łӉ�����k�サ�Ă����܂��B�g���Ɗ����̍����荇���a���L�x�ȊC��Ő������Ă����܂��B
���p�́A�h�g�A�Ă����A�t���C�A�����A���h�A�Ȃǖ��\�I��ł���B
|
 |
| �@�E�]�E���G�r |
|
Pariibacus japonicus
�Z�~�G�r�ȃ]�E���G�r��
��t�������p�܂Ő������Z�~�G�r�Ȃł��E�`���G�r�̂悤�ɗ��ʂ��邱�ƂȂ���Ⓙ�������ނ̃G�r���璿�d�����B
���ׂ������̌^�̊��ɐg�͋l�܂��Ă��āA�h�g�ł���łĂ������ŁA�قƂ�ǂ��Y�n�ŏ����A���ʂɍڂ邱�Ƃ͂���܂���B
|
 |
|
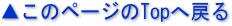 |