| 浦神支所の主要水揚げ水産物 |
| 海藻類:天草・ヒジキ |
| 貝類等:イセエビ・アワビ・トコブシ・サザエ |
| 魚類:カツオ・ブリ等多数 |
|
天然の良港と、熊野灘の好漁場に面する浦神は漁業によって栄えてきましたた。特に鰹漁は県下でも有数であった。鰹船の船主や、鰹節加工業者が何軒もあり、鰹節は区の主産物であった。しかし、沿岸漁業の不振によりその船も年々減り、今はその姿も消えた。華やかであった昔を知る人にとっては淋しき限りであろう。
その後、波静かな湾内で真珠に養殖が盛んになった。採れた真珠や母貝は、鰹節にかわる区の主要産物となった。湾内せましと並ぶ筏の列は、美しい浦神湾に人工的な美を加え、列車や車で通る人達の目を楽しませてくれたものである。
 昭和35年に、近畿大学水産研究所の実験場が、石原産業前に海面埋立地に設置された。ここではハマチの養殖を始め、マダコ、カンパチ、シマアジ、イシダイ、ヒラメなど多くの魚の人工ふ化、飼育などの研究が続けられ幾多の成果が挙げられている。 昭和35年に、近畿大学水産研究所の実験場が、石原産業前に海面埋立地に設置された。ここではハマチの養殖を始め、マダコ、カンパチ、シマアジ、イシダイ、ヒラメなど多くの魚の人工ふ化、飼育などの研究が続けられ幾多の成果が挙げられている。
一方、棒受網や一本づり、えび網やあわび、さざえ等の採貝も続けられ、漁業はやはり浦神の主産業です。 |
|
|
 |
| カツオ |
春から初夏に掛けて黒潮に乗って太平洋岸を北上する回遊魚で、夏から秋にかけて南下するのを戻りカツオと言い、型が大きくなります。
カツオのケンケン漁発祥の地として知られる串本では、沿岸カツオ漁の主流は曳き綱ケンケン漁になります。
黒潮の接岸、蛇行状況が大きく影響する沿岸カツオ漁ですが、衛星による接岸状況や海水温などのの活用で、安定した漁獲高を目指す試みも行われています。 |
|
| アジetc… |
アジ科の仲間にはマアジの他に、メアジ、オニアジ、マルアジ、アカアジ、ムロアジ、アカムロなどがいるが、いずれも側線の後にゼイゴと呼ばれる硬いウロコがあります。
煮魚、焼き魚、干物の他、少し大きめのアジは刺身でも美味しく、タタキなどにもされます。
主に刺し網漁、棒受け網漁などで獲られます。 |
|
 |
 |
| イセエビ |
外洋に面した浅い海の岩礁やサンゴ礁に生息し、昼間は岩棚や岩穴の中にひそみ、夜になると獲物を探しに出てきます。
食性は肉食性で、貝類やウニなどいろいろな小動物を主に捕食するが、海藻を食べることもあり、黒潮の打ち寄せる当組合で水揚げされるイセエビは人気があります。
漁法は主に、刺し網漁で、夕方に刺し網を仕掛け、早朝に網を上げます。漁期は10月から4月にかけてで、5月から8月の産卵期は資源保護を目的に禁漁とし、捕獲サイズも規制し資源の保全に努めています。
黒潮の押し寄せる海岸の磯際で育ったイセエビは、適度な締まりと黄金色の透き通った身で、お刺身、炭焼きなど、いろんな料理の素材として大人気です。
|
|
| アワビ |
磯際から水深20m程の岩礁に生息し、アラメ、ワカメ、コンブなどの褐藻類を食べ、主に夜行性の物が多く、日中は岩の間や砂の中に潜っています。
アワビの殻の背面には数個の穴が並んでいて、アワビではこの穴が4〜5個なのに対し、トコブシでは6〜8個の穴が開いていて見分けることができます。
アワビは高級食材として知られ、お刺身やステーキなどで食されます。
アワビは潜水漁で採捕され、稚貝の放流も盛んに行われ安定した資源を確保されて「います。
黒潮の押し寄せる海岸の磯際で育ったアワビは、適度な締まりと美しく透き通った身で、お刺身、炭焼き、ステーキなど、いろんな料理の素材として大人気です。
|
|
 |
 |
| サザエ |
磯際から水深30m程度までの岩礁に生息し、浅い場所には小型個体が多く、大型個体ほど深所に生息する傾向があります。夜行性で、夜になると岩礁を動き回り、海藻を歯舌で削り取って食べます。
刺身、あるいは殻ごと焼いた壺焼きで食べるサザエの壷焼きは有名で、最もポピュラーな食べ方として知られています。
サザエは潜水漁で採捕され、稚貝の放流も盛んに行われ安定した資源を確保されて「います。
|
|
|
|
|
|
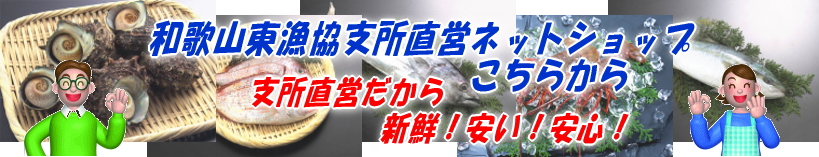 |
|
|
 |
 |
|
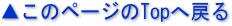 |
