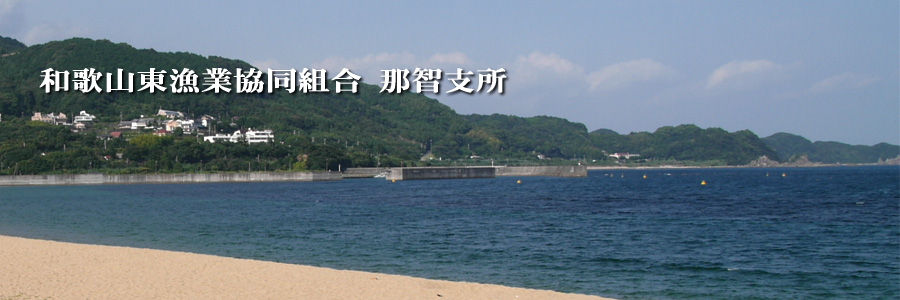| 那智支所の主要水揚げ水産物 |
| 海藻類:ヒジキ |
| 貝類等:イセエビ・アワビ・トコブシ・サザエ |
| 魚類:カツオ |
| その他:ナマコ |
|
 熊野那智大社を背に、前には那智の滝より注がれる那智の浜、そして熊野那智大社参拝と湯治で賑わう勝浦温泉…古くから門前町として栄えてきた那智の町並みですが、世界遺産登録に伴い、再び脚光を浴びてきました。 熊野那智大社を背に、前には那智の滝より注がれる那智の浜、そして熊野那智大社参拝と湯治で賑わう勝浦温泉…古くから門前町として栄えてきた那智の町並みですが、世界遺産登録に伴い、再び脚光を浴びてきました。
また、支所としてナマコ放流、イセエビ、アワビなどの放流を行っています。
南紀の観光地、勝浦温泉、世界遺産登録の熊野古道などを抱える那智支所は、地元で獲れた新鮮な魚介類を直接水揚げができるため、今後ますます期待寄せられるところです。
|
|
|
 |
| ひじき |
古座川の東海岸から田原へと延びる静かな海岸とその周辺で採れるヒジキは、丈が長く、太くてこしがあり柔らかいのが特徴です。
刈り採られたヒジキは、一旦、天日で干され、その後、大きな薪釜でじっくりと炊き上げます。そして再び天日干しをすると言う、全て手作業…
ヒジキにはカルシウムやマグネシウム、マグネシウム、鉄分、食物繊維などなど他にも多くの栄養がひじきには含まれています。 |
ヒジキ100gあたりの栄養成分
・たんぱく質 10.6g
・食物繊維 43.3g
・亜 鉛 1.8mg
・カルシウム 1400mg
・鉄 55mg
・マグネシウム 620mg
・ナイアシン 2.9mg
・ビタミンB1 0.36mg
・ビタミンB2 1.1mg
・葉 酸 84μg |
|
| イセエビ |
外洋に面した浅い海の岩礁やサンゴ礁に生息し、昼間は岩棚や岩穴の中にひそみ、夜になると獲物を探しに出てきます。
食性は肉食性で、貝類やウニなどいろいろな小動物を主に捕食するが、海藻を食べることもあり、黒潮の打ち寄せる当組合で水揚げされるイセエビは人気があります。
漁法は主に、刺し網漁で、夕方に刺し網を仕掛け、早朝に網を上げます。漁期は10月から4月にかけてで、5月から8月の産卵期は資源保護を目的に禁漁とし、捕獲サイズも規制し資源の保全に努めています。
|
|
 |
 |
| ナマコ |
海底をゆっくりと這って海底に降り積もって堆積した有機物を主な餌とし、触手でそれらを集めて食べます。
日本や中国では古来ナマコを食料として利用した長い歴史があり日本で主に食用とされるマナマコは体色からアカ・アオ・クロの3種に分けられます。
近年、那智支所でも需要の伸びにあわせ採取が盛んとなり、毎年、幼生を放流するなど資源の保全にも務めてきました。
|
|
| サザエ |
磯際から水深30m程度までの岩礁に生息し、浅い場所には小型個体が多く、大型個体ほど深所に生息する傾向があります。夜行性で、夜になると岩礁を動き回り、海藻を歯舌で削り取って食べます。
刺身、あるいは殻ごと焼いた壺焼きで食べるサザエの壷焼きは有名で、最もポピュラーな食べ方として知られています。
サザエは潜水漁で採捕され、稚貝の放流も盛んに行われ安定した資源を確保されて「います。
|
|
 |
 |
| アワビ |
磯際から水深20m程の岩礁に生息し、アラメ、ワカメ、コンブなどの褐藻類を食べ、主に夜行性の物が多く、日中は岩の間や砂の中に潜っています。
アワビの殻の背面には数個の穴が並んでいて、アワビではこの穴が4〜5個なのに対し、トコブシでは6〜8個の穴が開いていて見分けることができます。
アワビは高級食材として知られ、お刺身やステーキなどで食されます。
アワビは潜水漁で採捕され、稚貝の放流も盛んに行われ安定した資源を確保されて「います。
|
|
|
|